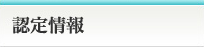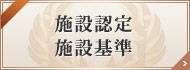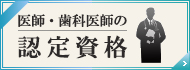診療科のご案内

心臓血管外科 (しんぞうけっかんげか)
部門紹介
当科は1959年(昭和34年)より心臓手術を開始しており、全国的にも歴史のある施設のひとつです。日本胸部外科学会指定施設、心臓血管外科専門医認定機構認定修練施設、ステントグラフト実施施設などに認定されています。現在7名(うち心臓血管外科専門医5名、同修練指導医3名、ステントグラフト実施医3名、同指導医1名)のスタッフと1~2名の研修医で、先天性心疾患、虚血性心疾患、弁膜症、大動脈瘤および末梢血管疾患と多岐に渡る循環器疾患手術を行っています。新生児から90歳以上の超高齢者に至る幅広い症例の手術を行っていることが当科の特徴で、大学病院以外の市中病院では数少ない施設のひとつです。
昨年3月をもって、長年にわたり当院のみならず、広島の心臓血管外科医療を支えてきた、吉田英生前副院長が定年退職されました。主に成人心臓疾患を受け持たれていましたが、先天性心疾患を受け持つ私(久持)と血管疾患を受け持つ柚木は、吉田先生のもとかなり自由に好きなことをさせていただいてきたと思います。多分野に渡る手術を行っている当科において、まさに扇の要と言える存在だったと実感しているとことです。この場をお借りして改めて御礼申し上げます。
代わって4月から 田村健太郎医師が赴任しました。フランス ボルドー大学や心臓病センター岡山榊原病院で豊富な経験を持ち、低侵襲手術などの新しい術式にも積極的に取り組む姿勢を見せてくれています。
新しい気持ちで様々なことに取り組んでいこうとしていたところでしたが、ご承知の様に新型コロナウイルス感染症が発生してしまいました。当科においても第1波といわれている4月~5月にかけて予定手術の延期をお願いせざるを得ない状況となってしまいました。6月からは通常にもどり、他施設からエキスパートの先生をお呼びして当院ではまだあまり行っていなかったMICSを指導していただくこともできていたのですが、第2波のさなか12月中旬には当院でクラスターが発生してしまい、手術・救急患者さんの受け入れ中止という事態になってしまいました。手術中止・延期をお願いさせていただいた患者様、紹介してくださる先生方、代わって急患を受けてくださった市内他施設のスタッフの方々にはお詫びと御礼を申し上げたいと思います。
この様な経緯のため当科の昨年2020年の症例数は2019年よりも減少していますが、心臓血管外科領域全体としては近年細分化、専門科が進み、手術成績の向上はめざましいものがあります。さらに低侵襲化という大きな流れがあります。反面、若手医師の外科離も課題となっています。当科においてもMICS、TEVAR/EVAR、TAVIといった、最先端、低侵襲治療に積極的に取り組んでいくと同時に、次世代を担う術者の育成にも力を入れていかなければならないと感じています。
本項を書いている2月中旬においてもまだ新型コロナウイルス感染症が完全に落ち着いたとは言えない状況です。スタッフ全員が各々自覚を持って生活をし、力を合わせてこの状況を乗り切らなければならないと思います。
皆さまには、引き続きご指導、ご鞭撻のほど、どうかよろしくお願い申し上げます。
令和3年2月
( 主任部長 久持 邦和 )
昨年3月をもって、長年にわたり当院のみならず、広島の心臓血管外科医療を支えてきた、吉田英生前副院長が定年退職されました。主に成人心臓疾患を受け持たれていましたが、先天性心疾患を受け持つ私(久持)と血管疾患を受け持つ柚木は、吉田先生のもとかなり自由に好きなことをさせていただいてきたと思います。多分野に渡る手術を行っている当科において、まさに扇の要と言える存在だったと実感しているとことです。この場をお借りして改めて御礼申し上げます。
代わって4月から 田村健太郎医師が赴任しました。フランス ボルドー大学や心臓病センター岡山榊原病院で豊富な経験を持ち、低侵襲手術などの新しい術式にも積極的に取り組む姿勢を見せてくれています。
新しい気持ちで様々なことに取り組んでいこうとしていたところでしたが、ご承知の様に新型コロナウイルス感染症が発生してしまいました。当科においても第1波といわれている4月~5月にかけて予定手術の延期をお願いせざるを得ない状況となってしまいました。6月からは通常にもどり、他施設からエキスパートの先生をお呼びして当院ではまだあまり行っていなかったMICSを指導していただくこともできていたのですが、第2波のさなか12月中旬には当院でクラスターが発生してしまい、手術・救急患者さんの受け入れ中止という事態になってしまいました。手術中止・延期をお願いさせていただいた患者様、紹介してくださる先生方、代わって急患を受けてくださった市内他施設のスタッフの方々にはお詫びと御礼を申し上げたいと思います。
この様な経緯のため当科の昨年2020年の症例数は2019年よりも減少していますが、心臓血管外科領域全体としては近年細分化、専門科が進み、手術成績の向上はめざましいものがあります。さらに低侵襲化という大きな流れがあります。反面、若手医師の外科離も課題となっています。当科においてもMICS、TEVAR/EVAR、TAVIといった、最先端、低侵襲治療に積極的に取り組んでいくと同時に、次世代を担う術者の育成にも力を入れていかなければならないと感じています。
本項を書いている2月中旬においてもまだ新型コロナウイルス感染症が完全に落ち着いたとは言えない状況です。スタッフ全員が各々自覚を持って生活をし、力を合わせてこの状況を乗り切らなければならないと思います。
皆さまには、引き続きご指導、ご鞭撻のほど、どうかよろしくお願い申し上げます。
令和3年2月
( 主任部長 久持 邦和 )

 English
English