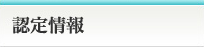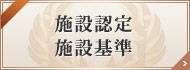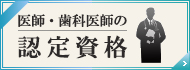診療科のご案内

脳神経内科 (のうしんけいないか)
脳神経疾患が疑われる急患の紹介(医療関係者の皆さまへ)
脳神経疾患が疑われ,緊急に対処が必要な(あるいはその判断に迷う)場合は,当院の電話交換で「今日の責任者(マネージャー)」を呼び出していただければ,できるだけ迅速に対応いたします.
脳神経内科での後期研修について
脳神経内科では,広島県だけでなく他都道府県からの当院の内科研修プログラムへの応募も歓迎しております.所属医局,入局の有無は問いません.当院2年+院外1年ですが,院外研修は豊富な連携施設から選ぶことができます.興味のある先生は是非お問い合わせ下さい.下記の紹介動画もぜひ一度ご覧下さい。
脳神経内科とは
脳神経内科は、一言で言えば「脳・脊髄・末梢神経・筋肉の病気を診る内科」です。以前は神経内科と呼ばれていましたが、神経科・心療内科などとの違いが分かりにくいということで、2018年以降に全国で名前の変更が行われています。ではどのような症状のある方が脳神経内科を受診すれば良いのでしょうか?脳神経内科で扱う症状は実に多彩です。
代表的な症状としては、「頭痛」、「めまい」、「しびれ」、「ふるえ」、「物忘れ」、「けいれん」、「うまく力が入らない」、「身体の脱力」、「ろれつが回らない」、「見にくい」、「筋肉のやせ」、「筋肉の痛み」、「意識障害」などがあります。このような症状でお困りの場合は、脳神経内科への受診をお勧めいたします。もちろん、これらの症状が全て脳神経内科の病気というわけではなく、他の診療科が扱う病気の場合もあります。その可能性が高いと判断した場合は、適切な診療科に紹介させて頂きます。
では、このような症状を起こす脳神経内科の病気にはどのようなものがあるでしょうか?扱う症状も多いので、病気も一般的なものから稀なものまで多岐にわたります。
主な病名としては、「脳卒中」、「頭痛(片頭痛・緊張型頭痛)」、「てんかん」、「アルツハイマー病」、「レビー小体病」、「血管性認知症」、「パーキンソン病」、「パーキンソン症候群」、「運動失調症」、「髄膜炎、脳炎」、「重症筋無力症」、「免疫性ニューロパチー」、「代謝性・遺伝性ニューロパチー」、「ミオパチー」、「筋ジストロフィー」、「急性脳症」、「筋萎縮性側索硬化症」、「球脊髄性筋萎縮症」などを診療の対象としております。
脳神経内科は、「脳卒中」、「てんかん発作」、「髄膜炎、脳炎」など救急医療を必要とすることの多い病気から、じっくりと診察をする必要がある「神経難病」までさまざまな病気を扱います。救急疾患については、救急科・脳神経外科などと協力し、迅速に対応させて頂きます。一方、救急以外の「神経難病」などが疑われる場合は、基本的には予約での外来診療を行っておりますので、まずはお近くの「かかりつけ」の先生を受診し、ご相談頂ければと思います。
脳神経内科の医師は、一般的な内科の経験を積んだ後、脳神経内科全般の専門的知識と技術を習得します(脳神経内科の専門医)。さらにその専門性にあわせて、脳卒中、脳神経血管内治療、頭痛、認知症、臨床生理、てんかんなどのさらに細分化された知識と技術を習得します。(各種学会の専門医) 当科の医師のプロフィールは、「医師紹介」の項をご参照ください。
当科では、入院された方につきましては、その病気にあわせた複数医師のチームで担当させて頂いております。したがって、外来担当医とはまた違う医師が担当になることもあります。また、限られた医療資源を最大限有効にするため、病院同士の連携、病院とクリニックの連携を重視しております。当院での治療が終了した場合には、他の病院への転院やクリニックへ紹介させて頂いております。ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。
 English
English